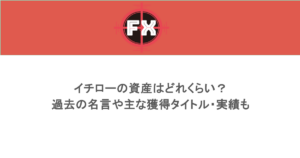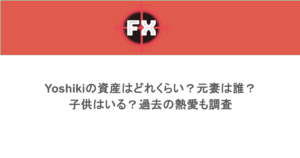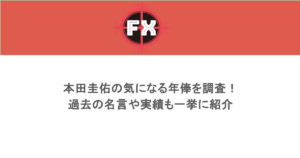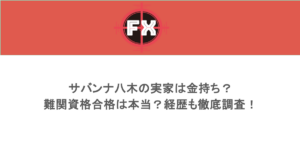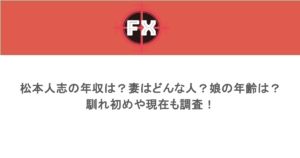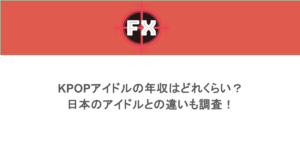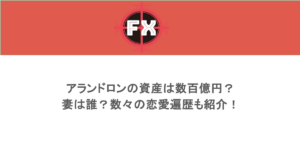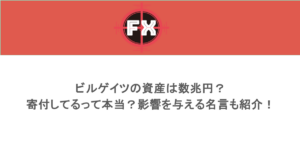コロナ禍が明け、在宅ワークなど様々な働き方が認められている昨今。様々な要因で現在務めている会社を辞め、他の会社に転職しようと考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、何も考えずに闇雲に退職すると、思わぬ損をする可能性があるので注意が必要です。今回この記事では、退職日はいつが得なのかを中心に、退職するときのポイントについて解説していきます。
退職日はいつが得?
お得になる退職日について紹介します。得になるかは基本的に社会保険料の支払いによって決まります。会社勤め中は会社の社会保険に加入しており、会社と従業員で半額ずつ負担していることを理解しましょう。
基本は月末
基本的に得になる退職日は「月末」になります。理由は、社会保険料の支払いが発生するからです。国民健康保険や国民年金などの料金は、手取りによって異なりますが4~7万円ほど。月末に退職することで、その分のお金が得になります。
社会保険料の支払いは、会社を退職した翌日から発生します。もし月の途中で退職した場合、退職した月の保険料も支払わなくてはいけません。月末に退職することで、社会保険料の支払いは来月分からになります。
扶養に入る場合は月末の前日まで
結婚など家族の扶養に入る場合は、月末の前日までに退職するとお得になると言われています。扶養に入った場合、その月から自分で支払わなくて良くなります。月末に退職した場合、その月の保険料を支払う必要があるため、月末の前日より前に退職すると良いでしょう。
退職日が半端な日になるので、事前に会社に相談が必要です。会社側も保険料の支払いが不要になったりとマイナスにならないはずなので、理解してくれるでしょう。
退職日を決める時のポイントを紹介
退職日を決める際のポイントについて紹介します。
社会保険の支払いで決める
先述した通り、月末以外に退職して、1日でも離職期間があると国民健康保険や国民年金の支払いが生じます。支払額は人によって異なりますが、4万円近くかかるため、月末に退職することで無駄な支払いを避けられます。
結婚など家族の扶養に入る場合は、当月分の支払いが生じる月末より前の日に退職しましょう
ボーナス日で決める
ボーナスが支給される7月や12月に退職する場合、しっかりとボーナスを受け取ってから退職したいと思うはずです。会社によっては、ボーナス支給日前に退職するとボーナス分が受け取れない可能性があります。
会社の就業規則や支給規定を確認し、ボーナスを獲得してから退職しましょう。
退職金の条件に合わせて決める
会社の勤続年数によっては退職金が発生します。多くの企業では「勤続年数2年以上」などと退職金が発生する条件があるため、事前に確認してから退職日を決めると良いでしょう。支給される退職金も計算しておくと、退職後のプランを決めやすいと思います。
転職先の入社日で決める
他の会社に転職する場合は「入社日の前日」が良いと言われています。これは先述の社会保険と同じで、一日でも国民健康保険や国民年金の支払いを発生させないためです。個人で支払う費用や切り替える手間を省くためにも、転職する際は前日に退職するのがオススメです。
退職して少し休んだり、転職先の準備をしたい人は、有休を使用して入社前日に退職するよう合わせましょう。
雇用保険の手当てで決める
会社を退職した後は、雇用保険によって一定期間手当を受け取れます。雇用保険は会社に入社すると自動で入ります。退職後に手当を受け取る条件は「退職日前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間がある」です。
退職後にしばらくの期間は雇用保険手当を受けたいと考えている人は、手当てが受け取れる条件を満たしているか確認してから退職日を決定しましょう。
雇用保険手当は、職業訓練を受けることで受け取れる期間を延ばせます。退職する際は、職業訓練に入ることも検討しておくと良いでしょう。
引継ぎ期間で決める
退職する場合でも、自分が担当していた業務は他メンバーに引き継がなくてはいけません。担当業務が多い場合、引継ぎに時間もかかります。もし、後任者がいない場合は、新たな人物の確保や部署異動など時間がかかる可能性もあるため事前に計算して退職日を決めると良いでしょう。
企業によっては退職後に引継ぎの質問で連絡してくることがあります。次の職場に支障が出るのでしっかり引き継げるよう準備しておきましょう。
職場の状況で決める
担当しているプロジェクトの進捗状況や、仕事が忙しい時は退職が難しい場合があります。忙しい時に十分な引継ぎができずに退職し、職場や取引先に迷惑が掛かる場合があります。同僚やプロジェクトメンバーに負担をかけない日に退職することをオススメします。
噂というのは想像以上に簡単に広まるため、変な噂が次の職場に入ると仕事に影響を与える可能性もあります。出来るだけ円満に退職するよう心がけましょう。
スムーズに退職申告する方法
退職する日程が決まれば、退職の申告や退職に向けた準備を行います。ここでは退職までの流れを紹介します。
上司に退職申告
「退職願」を用意して上司に退職する旨を申告します。申告するのは余裕をもって退職日の2か月前が良いでしょう。退職願が受理されれば「退職届」を提出します。退職届の様式については、企業によって異なるので人事担当者に確認すると良いでしょう。
退職の準備
退職届が受理されれば、退職の準備を始めます。会社から借りていた備品の返却や、引継ぎ資料を作成して担当した業務を引継ぎしましょう。
また、退職日に受け取る書類を確認しておきましょう。離職票や源泉徴収票などは何も言わずに渡される可能性が高いですが、退職証明書などが必要な場合は事前に申請しましょう。
有休消化する
引継ぎが終われば溜まっていた有休を消化すると良いでしょう。退職日の前日まで有休消化し、退職日に出社するのが一般的です。
有休消化の期間中はしっかりと休息し、次の職場への準備などを行いましょう。
退職日に出社し挨拶
退職日は出社してお世話になった人々へ退職の旨を挨拶します。挨拶では辞める理由などを問われると思いますが、会社の不満など会社を下げる発言は行わないほうが円満に退社できます。
また、退職日に受け取った書類は不備がないか確認しておきましょう。書類が足りない場合は郵送や受け取りにいく必要があります。
まとめ
今回は、退職日はいつが得なのか、退職日を決める際のポイントやスムーズな方法について解説しました。国民年金や国民健康保険の支払いは、1日だけでも月額支払う必要があるため、想定よりも高くなります。無駄な出費を抑えるためにも、退職は出来るだけ月末にしましょう。
退職を考えている人は、今回紹介した内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。
※日本のお仕事&給料.netも参考にしてみてください!

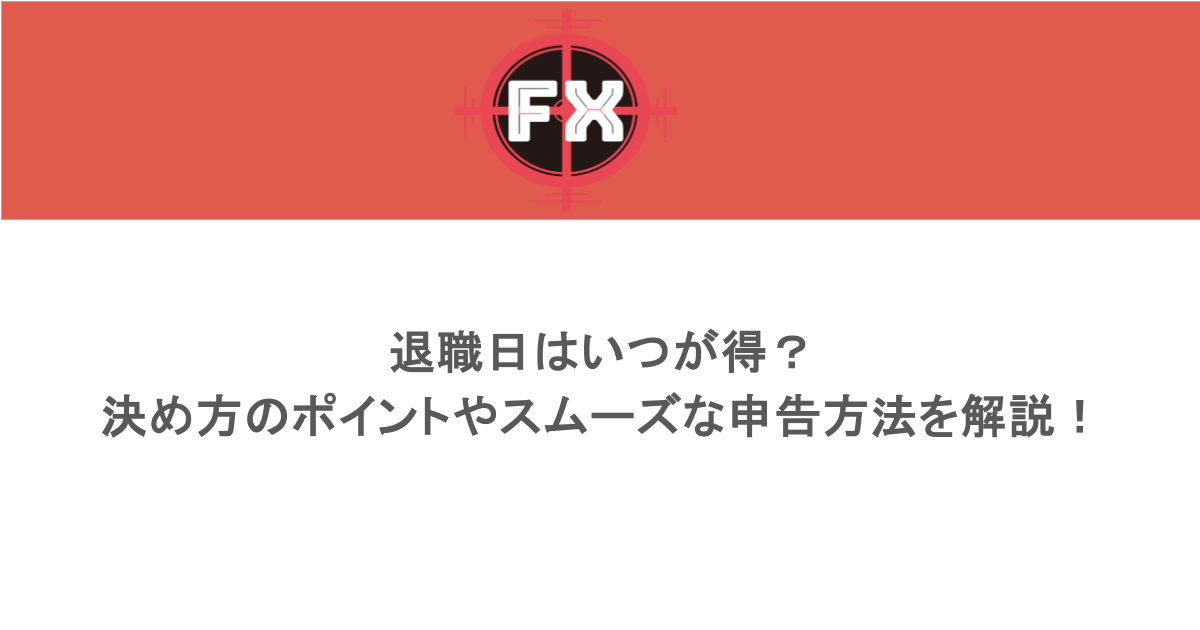
-1.jpg)