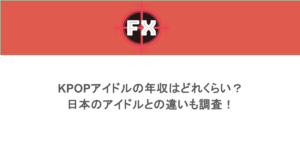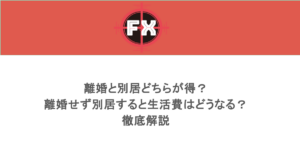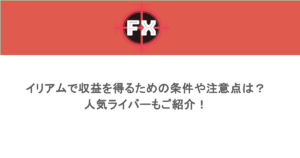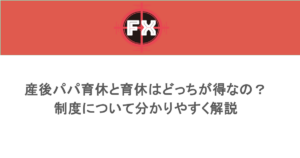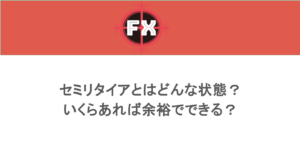居住や不動産投資のために住宅を購入すると、毎年かかる固定資産税。住宅の購入を検討しているものの、固定資産税について気になる人もいるのではないでしょうか。
今回この記事では、固定資産税がいくらになるのか一戸建てやマンションそれぞれ解説していきます。
固定資産税はいくらかかる?(一戸建て)
年間支払う固定資産税がいくらになるか、一戸建て(3000万円前後)の場合にかかる金額は平均10~15万円です。固定資産税は、住宅や土地の価値や築年数など様々な要素によって変化。納税金額は、地方自治体が調査や計算するため、確定申告のように自ら計算して提出する必要はありません。
計算方法
固定資産税を自ら計算する必要は無いですが、住宅を購入する前に事前に固定資産税がいくらになるか計算したいという人もいるでしょう。
固定資産税の金額は「固定資産評価額×固定資産税率(1.4%)」で求められます。固定資産評価額は土地と建物で異なるため、それぞれ固定資産税の計算方法を紹介します。
土地の固定資産税
土地の固定資産評価額は、各自治体が道路に面した土地1平方メートル当たりの価格(路線価)を基準に定められます。一般的に固定資産評価額は、地価公示価格の70%に調整されており、自治体が3年毎に見直しを行います。固定資産税評価額は「課税証明書」「固定資産課税台帳」「固定資産評価証明書」で確認可能です。
例えば土地を購入した際の価格が1000万円の場合、土地の固定資産税は以下の通りです。
- 固定資産評価額:1000万円×0.7=700万円
- 固定資産税:700万円×0.014=9.8万円
住宅の固定資産税
土地に建てられた住宅の固定資産評価額も土地同様に自治体によって3年に1回見直しします。
住宅の場合、建物の耐震等級や劣化などを含めて固定資産評価額が決まります。固定資産評価額は「再建築価格×経年減点補正率」で求められます。
再建築価格は、同じ土地に同じ住宅を建てた際に必要な費用です。経年減点補正率は、経年劣化の価値減少率を数値化したものです。主に50%から70%に収まります。
例えば住宅を1500万円で購入した場合、固定資産税は以下の通りです。
- 固定資産評価額:1500万円×0.5=750万円
- 固定資産税:750万円×0.014=10.5万円
木造の場合安くなる
一般的に固定資産税は建物の費用が高いほど税額が高くなります。また、経年劣化によって値段が下がるため、建築が高額になり劣化が起きにくい鉄筋コンクリートよりも木造建築の方が固定資産税が安くなります。
一般的に耐用年数は木造一戸建てが22年、鉄筋コンクリートマンションが47年と言われており、木造建築の方が評価額が下限まで下がるスピードが早いです。そのため最終的に木造建築の方が固定資産税を抑えられると言えるでしょう。
固定資産税はいくらかかる?(マンション)
マンションの場合の固定資産税の平均は新築の場合10~30万円と言われており、中古の場合10~20万円ほどになります。
計算方法
マンションの場合も固定資産税の求め方は一軒家と同じ「固定資産評価額×固定資産税率(1.4%)」で土地と建物それぞれ求められます。
マンションは土地の固定資産税を抑えやすい
建物の計算は一軒家と違いはありません。しかし、土地の固定資産税は敷地の中に複数の区分所有者がいることになるので負担額は比較的少なくなります。
固定資産税を抑えるには
固定資産税を抑えるには軽減措置を利用すると良いでしょう。ここでは現在利用できる軽減措置について紹介します。
土地の軽減措置
土地の広さに応じて軽減措置が用意されています。それぞれの軽減内容は以下の通りです。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下):評価額÷6
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):評価額÷3
例えば、敷地面積が250平方メートルの場合は200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの50平方メートルが一般住宅用地として計算されます。
住宅の軽減措置
住宅に関する軽減措置について紹介します。
新築住宅
2026年3月31日までに建てられた新築住宅で床面積が50~280平方メートルであれば住宅の固定資産税が半額になります。適用年数は3年間。3階以上の建物で耐火・準耐火建築物の場合5年間適用されます。
長期優良住宅
2026年3月31日までに建てた新築住宅が長期優良住宅に認定された場合は、固定資産税が半額になります。適用年数は5年間で3階以上の耐火・準耐火建築物の場合は7年間です。
長期優良住宅に認定されるには、「劣化対策」や「耐震性」「省エネルギー性」など複数の項目で条件を満たす必要があります。
既存住宅をリフォームした場合
既存の住宅を2026年3月31日までにリフォームした場合も、それぞれ軽減措置が用意されています。リフォームの内容と軽減額は以下の通りです。どれも1年間適用されます。
- バリアフリーや省エネ:固定資産税÷3
- 耐震:固定資産税÷2
- 長期優良化:固定資産税×3分の2
地域によって都市計画税も支払う必要がある
地域によっては固定資産税に追加して都市計画税を支払う必要があるので注意しましょう。
都市計画税は、都市計画法で指定されている地域に土地や建物を所有している人を対象にした税金です。指定される地域は主に市街地や商業施設として賑わっている場所が対象になります。
都市計画税の金額は「固定資産評価額×税率(0.3%)」で求めることが可能です。税率は自治体によって異なりますが0.3%という上限が設定されています。
都市計画税も軽減措置の対象
都市計画税も土地の軽減措置の対象になっています。軽減措置の内容は以下の通りです。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下):評価額÷3
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):評価額の3分の2
まとめ
今回は、固定資産税がいくらになるのか一戸建てやマンションの場合で解説しました。
固定資産税の平均額は一戸建ての場合10~15万円。マンションの場合10~30万円と言われています。
固定資産税は土地と建物それぞれ課され、木造の住宅は経年劣化が考慮され評価額が下限に達するまで速く、建物の固定資産税は鉄筋コンクリートが多いマンションに比べて安くなります。対するマンションは、敷地内に複数の区分所有者がいることになるため、土地の固定資産税は抑えやすくなっています。
一軒家やマンションの購入を考えている人は、固定資産税についても検討してみてはいかがでしょうか。
*生活に関するお役立ち情報は、こちらのサイト(refresh-nexco.jp)もチェックしてみてください。

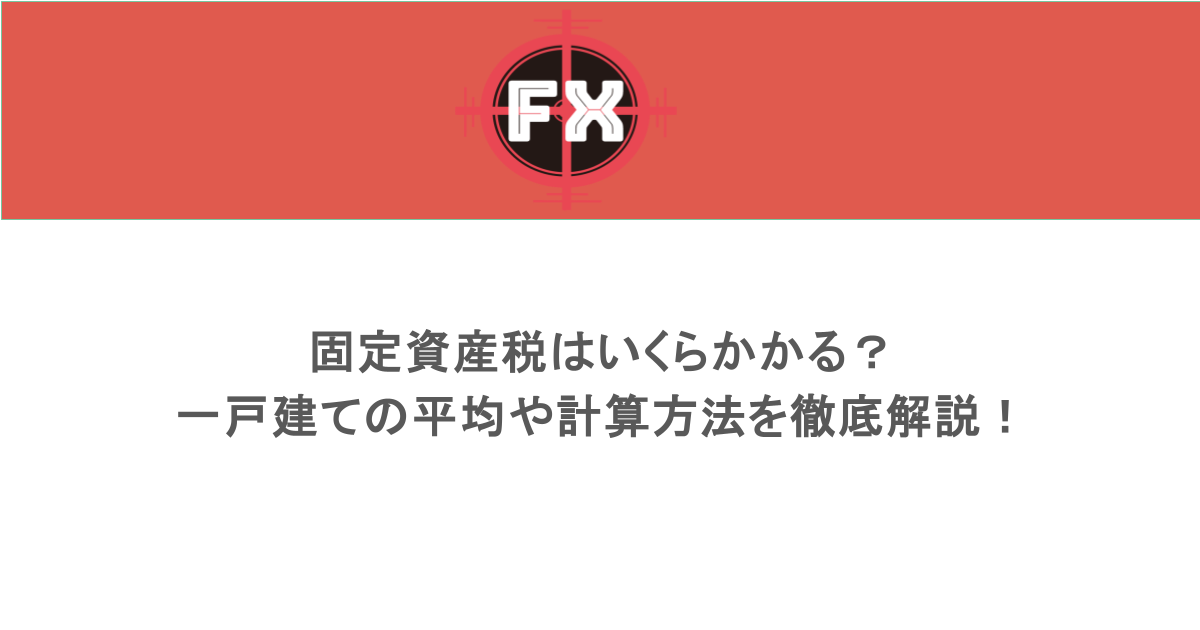
-1.jpg)